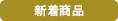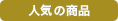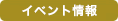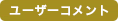- 酒(日本酒 地酒)の種別から探す
Search Sake by Category - 大吟醸酒
- 吟醸酒
- 純米大吟醸酒
- 純米吟醸酒
- 特別純米酒
- 純米酒
- 特別本醸造酒
- 本醸造酒
- 普通酒
- リキュール
- ビール
- 焼酎
- 発泡酒
- どぶろく
- スピリッツ
- その他の醸造酒
- ノンアルコール飲料
- 酒粕
- 酒蔵の食品
- 飲み比べ・ギフトセット
- ワイン(果実酒・甘味果実酒)
- 酒蔵オリジナル商品
- 酒(日本酒 地酒)の蔵元から探す
Search Sake by Breweries - 佐藤酒造
- 八丈島酒造
- 萩錦酒造
- 滝澤酒造
- 佐藤酒造
- 西岡本店
- 市野屋
- 森酒造場
- 中善酒造店
- 中央葡萄酒
- 大根島醸造所
- 盛田
- 老田酒造店
- 善哉酒造
- 東飯田酒造店
- 勲碧酒造
- 岡田屋本店
- 深野酒造
- 宮崎酒造店
- 蒲酒造場
- 蔵元一覧を見る
- 酒(日本酒 地酒)の銘柄から探す
Search Sake by Brand Name - 秀よし 純米吟醸酒 月涼み
- 阿櫻 大吟醸
- 純米大吟醸原酒 美郷錦仕込
- 阿櫻 精撰
- 阿櫻 本醸造
- 阿櫻 純米酒
- 阿櫻 純米吟醸超旨辛口
- 阿櫻 純米吟醸 吟の精
- 阿櫻 純米吟醸秋田酒こまち
- 阿櫻 純米大吟醸原酒
- 阿櫻 純米大吟醸
- 金冠黒松 純米にごり
- 大吟醸 鸞(らん)
- 酒母搾り酒 末摘花(スエツムハナ)
- 原田 純米吟醸あらばしり「ハル」
- 原田 特別純米酒ひやおろし「アキ」
- 純米吟醸 ひたち錦 50%
- 純米吟醸 雄町
- 純米大吟醸 酒母しぼりRei
- 原田 純米大吟醸 無濾過生原酒
- 銘柄一覧を見る
- 酒(日本酒 地酒)度から探す
Search Sake by Taste - 大辛口(+6.0~)
- 辛口(+3.5~5.9)
- やや辛口(+1.5~3.4)
- 普通(-1.4~+1.4)
- やや甘口(-1.5~3.4)
- 甘口(-3.5~5.9)
- 大甘口(-6.0~)
- 酒(日本酒 地酒)の価格帯から探す
Search Sake by Prices - ~ \3,000
- \3,001 ~ \6,000
- \6,001 ~ \9,000
- \9,001 ~ \12,000
- \12,001 ~ \15,000
- \15,001 ~

いそのさわ
銘柄酒:磯乃澤
創 業:明治26年
杜 氏:
住所:福岡県うきは市浮羽町西隈上1の2
ホームページ:
Brand:
Initiation:
Master Brewer:
Address:Fukuoka
明治26年、現会長の祖父高木喜三郎により創業された。高木家は、源を日田に発する耳納山と、筑後川に挟まれ東西に細長い筑後平野の東部、すなわち、福岡県浮羽郡浮羽町(旧椿子村)の県道に面して、日田市へ四里、久留米市へ七里の位置にあった。
家業は代々紺屋で、広い家の中には絶えず藍の匂いが鼻をつき、その匂いが家の人達の体臭のようになっていた。喜三郎は、両親から家業を継ぐよう勧められたが、頭から藍に染まり天候に気を配りながら仕事を進めなければならぬいかにもじめじめした感じの紺屋をどうしても継ぐ気になれなかった。しかし、喜三郎は、やりたい仕事があったわけではなかった。 喜三郎は19歳になると、浮羽郡浮羽町(旧大石村)古川の練山次三郎の姪、マツヨと結婚した。妻を娶った喜三郎は急に高木家の一切の責任がずっしりと肩にのしかかってきたような感じになった。
そんな或る日、近所の林田彦助の勧めで材木の仲買いを思いたち、日田市から杉材を仕入れ、久留米市の酒屋に売って大儲けをした。この活気がありいかにも落ちついた雰囲気の漂う酒屋に影響を受け、酒屋を始めようと決心するのであった。 当時の日本は、旧来の文化と、異国の文化の交流が活発に行われるようになり、中央から遠く離れた九州久留米の町にも、洋服を着た人が歩くのを見受けられるようになっていた。
喜三郎は、酒屋を創業するに当たって、自分の生活態度を改めることから始めた。そして、自宅の紺屋を少しづつ酒屋に適するように改築を行い、その一方、自分自身は酒造りの資料を各方面から収集し、酒造りの勉強を独学で進めた。建物、道具、材料も揃い、明治26年12月1日に待望の火入れが行われ、酒造りの記念すべき日となった。
初代杜氏は鳥越五平で、15歳から当時福岡県で最も酒造の盛んであった城島の酒屋に奉公し、人に負けない技術を身につけていたが、地域性(出身地)の強い蔵男達の中では、他国者(浮羽町出身)といびられ続け、25年間努力してもまだ蔵一にもなれず三役どころで使われていた。そこを喜三郎に抜擢され杜氏としての望外の地位を与えられた。五平は城島方面で自分と同じ扱いを受けていた蔵男達を磯乃澤へ呼び、当時は若い蔵男達の血涙をしぼることが蔵男教育であると考えられていた古いしきたりに反対し、しっかりチームワークをつくり酒造りに努めたのである。
(いそのさわHPより引用)