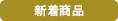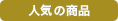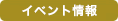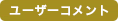- 酒(日本酒 地酒)の種別から探す
Search Sake by Category - 大吟醸酒
- 吟醸酒
- 純米大吟醸酒
- 純米吟醸酒
- 特別純米酒
- 純米酒
- 特別本醸造酒
- 本醸造酒
- 普通酒
- リキュール
- ビール
- 焼酎
- 発泡酒
- どぶろく
- スピリッツ
- その他の醸造酒
- ノンアルコール飲料
- 酒粕
- 酒蔵の食品
- 飲み比べ・ギフトセット
- ワイン(果実酒・甘味果実酒)
- 酒蔵オリジナル商品
- 酒(日本酒 地酒)の蔵元から探す
Search Sake by Breweries - 佐藤酒造
- 八丈島酒造
- 萩錦酒造
- 滝澤酒造
- 佐藤酒造
- 西岡本店
- 市野屋
- 森酒造場
- 中善酒造店
- 中央葡萄酒
- 大根島醸造所
- 盛田
- 老田酒造店
- 善哉酒造
- 東飯田酒造店
- 勲碧酒造
- 岡田屋本店
- 深野酒造
- 宮崎酒造店
- 蒲酒造場
- 蔵元一覧を見る
- 酒(日本酒 地酒)の銘柄から探す
Search Sake by Brand Name - 秀よし 純米吟醸酒 月涼み
- 阿櫻 大吟醸
- 純米大吟醸原酒 美郷錦仕込
- 阿櫻 精撰
- 阿櫻 本醸造
- 阿櫻 純米酒
- 阿櫻 純米吟醸超旨辛口
- 阿櫻 純米吟醸 吟の精
- 阿櫻 純米吟醸秋田酒こまち
- 阿櫻 純米大吟醸原酒
- 阿櫻 純米大吟醸
- 金冠黒松 純米にごり
- 銀盤 限定生貯蔵 純米大吟醸 播州50
- 銀盤 純米大吟醸中汲み原酒 播州50
- 銀盤 純米大吟醸 富の香しぼりたて生原酒
- 大吟醸 鸞(らん)
- 酒母搾り酒 末摘花(スエツムハナ)
- 銀盤 純米大吟醸 播州50ひやおろし
- 原田 純米吟醸あらばしり「ハル」
- 原田 特別純米酒ひやおろし「アキ」
- 銘柄一覧を見る
- 酒(日本酒 地酒)度から探す
Search Sake by Taste - 大辛口(+6.0~)
- 辛口(+3.5~5.9)
- やや辛口(+1.5~3.4)
- 普通(-1.4~+1.4)
- やや甘口(-1.5~3.4)
- 甘口(-3.5~5.9)
- 大甘口(-6.0~)
- 酒(日本酒 地酒)の価格帯から探す
Search Sake by Prices - ~ \3,000
- \3,001 ~ \6,000
- \6,001 ~ \9,000
- \9,001 ~ \12,000
- \12,001 ~ \15,000
- \15,001 ~

ふじの井酒造
銘柄酒:ふじの井
創 業:明治19年(1886)
杜 氏:
住所:新潟県新発田市藤塚浜1335
ホームページ:http://www.sake-fujinoi.com/
Brand:
Initiation:
Master Brewer:
Address:Niigata
■”ふじの井”の由来
新潟と村上を結ぶ国道113号線のほぼ中程に、日本海の怒涛と果てしなし砂丘、美しい赤松林に囲まれた景勝の地【藤塚浜】にふじの井酒造があります。
昔から新潟-村上間の海岸地帯には、良い水が出ないとされていましたが、藤塚浜にだけは古くから伝わる神秘の井戸がありました。汲めども尽きせぬこの井戸水は、近郷近在から舟水や飲料水を求める人々の貴重な潤いの地であったといい、人呼んで“不二の井戸”と称しました。この井戸水で酒を醸すと醗酵旺盛にしてうまい酒ができることから、銘酒“ふじの井”が誕生しました。
地下20メートルの原水は朝日・飯豊連峰の伏流水といわれ、100年もの歳月をかけてたどり着くといいます。口に含むとわずかに甘味を感じ、酒造りが難しいとされる軟水系ですが不思議と醗酵が旺盛で、辛口、まろやかな酒に仕上がります。
■ふじの井酒造の創業
明治19年(1886)9月、藤塚浜で大火があり全村500余世帯の集落は一夜にしてそのほとんどを焼失しました。その大火の跡に只一つ、現在一号蔵とよばれている蔵だけが焼残り、村人を驚かせたといいます。初代政太郎は火から酒蔵を守るために酒蔵の扉を閉め、扉の隙間に味噌を塗り込みこの蔵を守り通しました。今でもこの酒蔵の天井板に生々しく当時の猛火を想わせる焦跡が刻み込まれています。紫雲寺潟の干拓が功を奏し、村松浜に代官所ができ、北前船が繁く寄港する様になって藤塚浜も次第に発展した矢先の大火災で、村人達の大半が当時「鰊景気」に湧く北海道:小樽近くの高島海岸に移住して行きました。平成の今も、北海道の高島町と藤塚浜の盆踊りが同じであることから当時が偲ばれます。
徳川末期頃、仲間三人衆:桶屋と船主と地主が酒造りを始めたともいいます。大火から酒蔵を守った政太郎が一人残り、この酒蔵を継承再建したことからこれを記念して、大火に遭った酒蔵を一号蔵と命名し創業を明治19年9月としました。
(ふじの井酒造HPより引用)