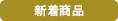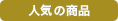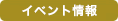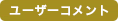- 酒(日本酒 地酒)の種別から探す
Search Sake by Category - 大吟醸酒
- 吟醸酒
- 純米大吟醸酒
- 純米吟醸酒
- 特別純米酒
- 純米酒
- 特別本醸造酒
- 本醸造酒
- 普通酒
- リキュール
- ビール
- 焼酎
- 発泡酒
- どぶろく
- スピリッツ
- その他の醸造酒
- ノンアルコール飲料
- 酒粕
- 酒蔵の食品
- 飲み比べ・ギフトセット
- ワイン(果実酒・甘味果実酒)
- 酒蔵オリジナル商品
- 酒(日本酒 地酒)の蔵元から探す
Search Sake by Breweries - 佐藤酒造
- 八丈島酒造
- 萩錦酒造
- 滝澤酒造
- 佐藤酒造
- 西岡本店
- 市野屋
- 森酒造場
- 中善酒造店
- 中央葡萄酒
- 大根島醸造所
- 盛田
- 老田酒造店
- 善哉酒造
- 東飯田酒造店
- 勲碧酒造
- 岡田屋本店
- 深野酒造
- 宮崎酒造店
- 蒲酒造場
- 蔵元一覧を見る
- 酒(日本酒 地酒)の銘柄から探す
Search Sake by Brand Name - 秀よし 純米吟醸酒 月涼み
- 阿櫻 大吟醸
- 純米大吟醸原酒 美郷錦仕込
- 阿櫻 精撰
- 阿櫻 本醸造
- 阿櫻 純米酒
- 阿櫻 純米吟醸超旨辛口
- 阿櫻 純米吟醸 吟の精
- 阿櫻 純米吟醸秋田酒こまち
- 阿櫻 純米大吟醸原酒
- 阿櫻 純米大吟醸
- 金冠黒松 純米にごり
- 大吟醸 鸞(らん)
- 酒母搾り酒 末摘花(スエツムハナ)
- 原田 純米吟醸あらばしり「ハル」
- 原田 特別純米酒ひやおろし「アキ」
- 純米吟醸 ひたち錦 50%
- 純米吟醸 雄町
- 純米大吟醸 酒母しぼりRei
- 原田 純米大吟醸 無濾過生原酒
- 銘柄一覧を見る
- 酒(日本酒 地酒)度から探す
Search Sake by Taste - 大辛口(+6.0~)
- 辛口(+3.5~5.9)
- やや辛口(+1.5~3.4)
- 普通(-1.4~+1.4)
- やや甘口(-1.5~3.4)
- 甘口(-3.5~5.9)
- 大甘口(-6.0~)
- 酒(日本酒 地酒)の価格帯から探す
Search Sake by Prices - ~ \3,000
- \3,001 ~ \6,000
- \6,001 ~ \9,000
- \9,001 ~ \12,000
- \12,001 ~ \15,000
- \15,001 ~

若戎酒造
銘柄酒:若戎
創 業:嘉永6年(1853)
杜 氏:
住所:三重県伊賀市阿保1317
ホームページ:
Brand:
Initiation:
Master Brewer:
Address:Mie
■若戎の水
酒づくりに最適な恵まれた名水を使用
銘醸地に名水あり、といわれるように、名酒を仕込むのに欠かせない水。日本は山紫水明といわれ、よい水に恵まれています。しかし、飲んでおいしい水と酒づくりの名水とでは少し内容が異なります。
酒づくりの名水の定義とは、酒が嫌う鉄分やマンガンが少なく、醗酵に有用な成分が適度に含まれ馥郁とした風味を醸す水となります。科学の発達した現代では、その成分はある程度知ることが出来ますが、人工的に生み出すことは出来ません。
若戎では、四方の山々から流れでた清水が地下水となり、きめ細かい酒を醸す軟水の伏流水として豊富に溢れています。この恵まれた良水が若戎の酒づくりにはかかせません。
■若戎の酒米
地元・伊賀で作られた良質の山田錦
清酒の原料として使われる米は酒造米や酒米と呼ばれ、酒米の横綱は山田錦といわれています。事実、酒造業界で最高権威があると言われる全国新酒鑑評会には山田錦で造ったものでないとまず入賞は難しいと言われています。
山田錦は極めて高価ですが倒伏に弱く、病虫害に弱い、収量も少ないということでこの米を作る農家は少なく、兵庫県で作られる山田錦は手に入り難いお米となっていました。そこで昭和61年(1986)、先代・重藤久一が三重県でも山田錦を作るように農家に働きかけ、伊賀地方でも良質の山田錦(三重山田錦)が採れる様になり、必要量を確保できるようになりました。
(若戎酒造HPより引用)